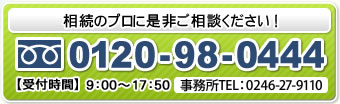相続とは?
相続とは、人の死亡を原因として、その人の財産が家族や親族に承継されることです。
承継される財産には、現金、不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。
なお、相続人の範囲や相続の優先順位などは、民法で規定されています。
承継される財産には、現金、不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。
なお、相続人の範囲や相続の優先順位などは、民法で規定されています。
名義変更はどうやってやるのですか?
亡くなった方の財産の名義を変えるには、 相続人全員で話し合いをして誰の名義にするか決める必要があります。
この相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
次に遺産分割協議書に話し合いによって決まった内容をまとめます。
名義変更に必要な書類を集めます。
名義変更に必要な書類は、以下の通りです。(不動産の場合)
・亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
・亡くなった人の住民票の除票
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書(法務局)
・遺産分割協議書(自分たちで作成する)
亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)は、 異なる市町村役場に点在していることがほとんどです。
次に遺産分割協議書に話し合いによって決まった内容をまとめます。
名義変更に必要な書類を集めます。
名義変更に必要な書類は、以下の通りです。(不動産の場合)
・亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
・亡くなった人の住民票の除票
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書(法務局)
・遺産分割協議書(自分たちで作成する)
亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)は、 異なる市町村役場に点在していることがほとんどです。
相続税の申告は必ずしなければいけないのか。
遺産は原則として課税の対象となりますが、相続税は相続額が一定額を超えた場合に申告して納税することとなっています。
たとえば、相続税には基礎控除があり、3000万円+法定相続人×600万円までは相続税がかかりませんので、申告する必要はありません。※平成27年1月より
また、配偶者には相続税軽減措置があり、法定相続分相当額(その額が16000万円に満たないときは、16000万円)までは非課税になります。
たとえば、相続税には基礎控除があり、3000万円+法定相続人×600万円までは相続税がかかりませんので、申告する必要はありません。※平成27年1月より
また、配偶者には相続税軽減措置があり、法定相続分相当額(その額が16000万円に満たないときは、16000万円)までは非課税になります。
相続財産の評価はどういう方法で?
地上権、定期金に関する権利などは評価方法が法律で定められていますが、その他の土地、建物など大部分は時価により評価します。
①宅地その他の土地
①宅地その他の土地
路線価方式と倍率方式がありますが、地域でその扱いがわかります。また小規模宅地などには特例もあります。
②農地、山林倍率方式と宅地比準方式のいずれかで評価します。
③借地・貸地地域によって違いますが、借地権を6~7割とみるのが普通です。貸地の場合は借地権分を引くことになります。
④家屋固定資産税の評価と同じです。県税事務所や市町村役場で確認できます。
⑤借家・貸家地域によって違いますが、貸家は通常の家屋の評価額の6~7割で評価します。
⑥株式・上場株は取引所での時価
・気配相場のある株は3種類あり、評価方法が違います。
・非上場株の場合はかなり複雑な評価方法となります。
⑦ゴルフ会員権取引相場の7割で評価